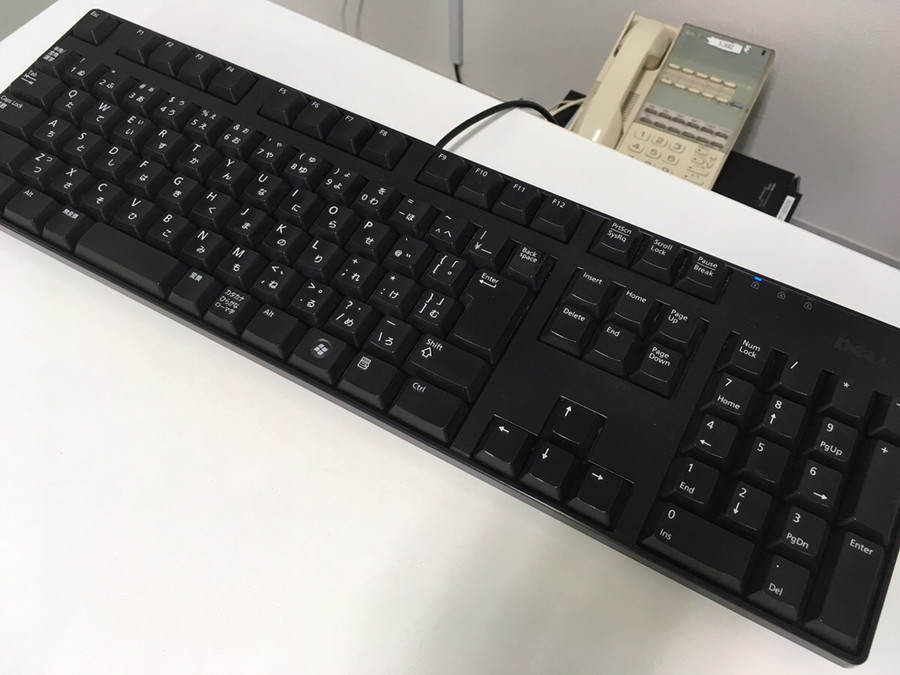SNSが流行している現代においては、ツイッターフェイスブック、インスタグラムなどを使って、誰でも手軽に情報発信ができます。さらに、SNSが流行る以前の時代は、個人の情報発信の主流はブログでした。一般ユーザー以外にも、かつてはたくさんの著名人が自分専用のブログを開設していたものです。では、それよりも前の時代の人々は、どうやって情報発信をしていたのでしょうか。
答えは「ホームページ」です。インターネット黎明期の時代は、たくさんの人が1からホームページ制作に勤しんでいました。自ら構築したホームページに日記や写真、イラストなどを掲載して、表現欲を満たしていたのです。そんな時代においては、今では使われなくなった専門用語なども少なくありませんでした。
キリ番
ホームページの入り口に置いてある「アクセスカウンター」がキリのいい数字になるという意味です。ようは、遊園地や水族館などのキャンペーンでよくある「○○人目のお客様」みたいなものですね。キリ番を踏むことで、ホームページの管理人が褒めてくれたり、イラストのリクエストを受け付けてくれたりといった恩恵を受けることができました。
ダミーエンター
その名の通り、ニセの入り口です。注意書きや説明を読めば、本当の入り口を発見できます。イラスト系のサイトにとくに多く、サイトの「入口のバナー」をクリックすると「注意書きの読めない人は出て行ってください」みたいな喧嘩腰の偽ページに飛ばされるトラップでした。「注意書きを読まない方が悪い」って言われると何も返せませんが、不愉快に感じる人は多かった記憶があります。
同盟
SNSが発達して居なかった時代は、友人や仲間を見つけるために「○○同盟」というものがいくつも作られました。揚げ物大好き同盟や、深夜番組大好きなど、特定の趣味嗜好の同盟となることで、閲覧者に「自分はこんな人間ですよ」とアピールする効果も持ち合わせていました。同盟となった暁には、自身のホームページにバナーを掲載するのがお決まりでしたね。
テレホーダイ
ダイヤルアップ接続だった時代は、インターネットに繋いだ時間分だけ料金が増えていくシステムでした。のちにテレホーダイという、23時~8時までは接続し放題という定額サービスが作られたことを皮切りに、みんな夜通しインターネットを楽しんだものです。